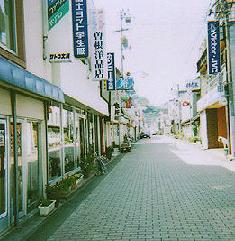NO.3 ~芸術と趣味の問題について~
前回の寄稿に添えた3枚の写真を見直すと、改めて過疎地の悲惨さをつくづくと自覚し直します。
そのような環境の中で発見したのが、人間にとって構造的なものは趣味や娯楽であり、芸術は過剰なものである、という定義です。
では人間にとって芸術はどんな意味を持つのか、芸術と趣味娯楽を比較することで考えてみましょう。
普通の芸術論の本をひも解くと、芸術も趣味娯楽もともに「自己目的的」である、と書いてあります。その上で、芸術は、創作者・作品・鑑賞者、という3元構造になっています。一方、趣味は参加者の内部だけでその行為を行うことがすべてであり、作品も鑑賞者も存在する必要のない1元構造である、それが芸術と趣味娯楽の違いである、と。この説明は確かにそのとおりなのですが、僕はとにかくこのHPでは、実感主義、経験主義から始めることにしようと考えています。
まず、全ての先入観を捨てて、事実のみを直視して考えてみましょう。
すると、自己目的的、という原理そのものが、僕には非常にロマンティックな、芸術を崇高なものと見過ぎる気風の中で生まれた言葉のように思えます。自己目的的というのは、たとえばものを切るためにナイフを作るというような他目的的な行動と異なり、まったく自発的で実用的目的を持たないという意味ですが、本当にそうでしょうか。
確かにCMの映像は最終的には商品を売ることを目的としており、この点では純粋作品は自己目的的です。けれど再度考えてみると、少なくとも現代、芸術の大衆化と商品化、そして学校教育、公共機関の受入体制の整った今日では、ほとんどの人間は「賞賛」や「受賞」を目的に芸術行動をとっています。
実際、芸術学校の先生も、自分で楽しんでいるうちはまた趣味でしかない、観客の心を捉えて揺さ振るような作品を作って入賞するようにと指導しているでしょう。また、北野たけしのTV番組「誰でもピカソ」でしたか、これを見ていると、現代社会では芸術家を志す人間がいかに功利的で、受けねらいで創作しているか嫌になるほど見えてきます。
芸術は自己目的的であると素直に言えた時代は、素朴なロマンティックな時代であったといえるでしょう。
個人映像作家にしても、今30代の半ばの世代は非常に自己プロデュースの才に富み、権威と結びつくのが実に上手ですね。特に芸大出身者はそうです。僕はこの世代から後は「芸術家は死んだ」と言っていいと思います。
元に帰りますが、芸術は常に鑑賞者と批評、評価を含む3元的な場に成立するがゆえに、決して自足せず、他目的的になります。この点、当事者たちがそれを実行することだけで満足する1元的構造の趣味娯楽は、確かに自己目的的だといえます。
しかし、他方、1元構造でない趣味もあります。これは例えば囲碁、将棋、麻雀などがそうです。この趣味にはプロが存在します。彼らの行ったゲームは新聞雑誌テレビで報道され、棋譜という作品の形も残り、批評もされます。この意味では3元構造です。しかし、これらのゲームを人は芸術であるとは思いません。なぜでしょう。
それは三つの点で、芸術と異なっているからです。
第一に、これらのゲームは勝ち負けが客観的に判明しますが、芸術の評価は主観的なものなので、勝ち負けをはっきりと付けにくい場合が多くあります。
第二は、これは第一の結果を生む原因で、もっとも大切なことですが、ゲームには厳格なルールがあります(例えば、2歩は反則負け、など)。
一方芸術は、規則を自ら変化させうるという意味で、「自己規定的」な存在です。芸術は芸術の概念すら自分の作品を通して更新し、その外延と内包を増殖しうる、ヌエのような創造行為です。例えば、パフォーマンスという名称を使えば、観客の前で日常生活を提示するだけでも芸術になります(ジャック・スミス)。観客に料理を接待することも立派なパフォーマンスです(佐々木健)。
芸術は、これら反芸術さえ自在に取り込む貪欲で巨大な子宮なのです。
最後に、囲碁将棋麻雀は、たとえどのような名勝負であっても、それを鑑賞する人間の心に与える感動の質が、芸術と比べるときわめて単調です。
芸術は、人間の感情を多種多様に刺激して、「未知の感情」すら生み出します。エロティシズムやセンチメンタリズムのような卑俗な感情から、金井勝作品のような「不気味な神聖さ」まで、実に豊かな感情を喚起します。さらに、反芸術の子どもである概念芸術は、感情に作用することさえも拒否して、記号論的意味作用を提示するだけで、観客の情動を放置する、という対極的な立場に立ちますが、いずれにしても感情の喚起の種類が豊富であることには間違いありません。
芸術は創造者、作品、鑑賞者という3元構造を持ち、「規範の自己規定性」、「鑑賞者に訴える感動の多様さ」、を条件として持つ人間の文化的行為です。
ところで、だから芸術は趣味や娯楽と比べて高級である、という思い込みは僕にはありません。かつて稲垣足穂は、どこにも発表せず、だれにも読まれなかった詩でさえも(つまり、それは1元的な存在ですから定義的には趣味娯楽の領域に入りますが)、それを書いたあなたは立派な詩人である、と言ったものですが、詩に限らず、川に糸を垂らしてアマゴを狙う釣り人と、芸術大学を出て傑作を狙っている芸術家の卵と、どちらが精神性が高いかは、まったく別の問題のように思えるのです。
さて、芸術と趣味の問題について考察してきましたが、非常に興味深い例について話すのを忘れていました。それは「小型映画」と「実験映画」の比較です。両者はともにフィルムを使った表現形式を取りながら前者は趣味とみなされ、後者は芸術として社会に認知されるにいたりました。趣味と芸術の問題を考えるにはとても興味深い素材です。
これに関してまた次回に語ることにしましょう。
 |
 |
|
庭の一隅。
ヤブカンゾウ、カキドオシ、ミツバ、
モロヘイヤを育てている。
細長い葉がヤブカンゾウで和名「憂い忘れ草」、
不眠症に効能がある。
|
6畳の書庫と5歳の長男。
本棚作りから天井張り、床のコンクリート塗りまで
全て自作。
小型映画に関しては日本一のコレクションがある。
|
NO.4 ~実験映画と小型映画の芸術性~
前回の原稿は、,芸術と趣味の違いに関してちょっとした定義を行い、両者を比較しました。そこで、「小型映画」と「実験映画」は、この問題を考える上で絶好の素材だといいました。両者の歴史を少し振り返ってみましょう。
日本で、あるいは世界で小型映画という趣味が流行したのは1920年代の半ばからです。これは、演劇における小劇場運動とリンクしていて、反商業主義演劇の気運が盛り上がった時期に、パテベビーという9・5ミリカメラ、プロジェクターや、16ミリ機器が商品化されたことで、先進諸国に大いに広がりました。
大いに広がった、といっても、これらの機材が非常に高価だったため、有閑階級(idle&rich)にのみ許される特権的な趣味でした。戦後もこの傾向は続いていて、1965年頃にスーパー8、シングル8が発売されるまでは、小型映画を楽しむ階級は相当の御金持ちでした。戦前は特に特権的ブルジョアジーに限られていたと言ってもいいでしょう。会社経営者や医者、庄屋クラスの大地主とその子息など、100人に一人もいない優雅な趣味でした。
さらに、小型映画は大都市のみに流行した趣味でした。この事は「実験映画」に関しても同様です。両者とも大都市でなければ生息できない、アーバンな趣味なのです。
富裕な階級であること、大都市にのみ存在すること、この2つの条件は嫌でも小型映画作品の中に、またその批評の中に、特有のイデオロギーを内包させます。例えば、革命というものを最も恐れるのは有閑階級です。
さらに、戦前は明治憲法下であったということは絶対的な制約として作品を規定しました。よりよき国民であること、愛国者であることは、あえて言う必要のない空気のようなものでした。そして「都市住民」であることは「流行に敏感である」ことと同義ですので、彼らは要するに道徳的に真面目で、そして新しもの好きでした。
目を転じてプロレタリア芸術家、プロキノの連中を見てみましょう。興味深いことにプロキノの主要メンバーだった、佐々元十、岩崎昶なども戦前に大学を出ているのですから階級的には小型映画を趣味とする人々と大差ありません。ただ彼らは共産主義者でしたので、プロレタリア革命を目標にし、この点で普通の小型映画作家とイデオロギー的には対照的でした。
けれど「都市に住む有閑階級」という面では両者は同じですから、新規なものへの好奇心はともに強く、その傾向はプロキノ側のほうにより顕著です。彼らは1920年代の末までは、徹底的なアヴァンギャルディストでした。後に彼らは、「党の方針として」その新奇好みの性格を、意識的に隠すようになり、批評も内容主義、政治主義に変化していきますが、体質的には本来、戦前の小型映画作家たちは、プロキノを含めて前衛嗜好だったといってよいでしょう。
さらに戦前の知識人の間では、基本的に「前衛映画」は非常に熱心に受け入れられました。ドイツ表現主義、フランス印象主義、ドイツ室内劇派、リズム論、モンタージュ論、全てが熱狂的に受容されています。「伯林ー大都会交響楽」は絶対映画的要素と、モンタージュを基本とした非常にスタイリッシュな記録映画ですが、これは大ヒットしました。岩崎昶などは、「おお、絶対映画よ」と熱狂的な賛辞を書いています。(後に彼は、前衛映画を、ブルジョアの退廃芸術と見なす発言をするのですが)。
こうして、戦前は、都市に住む知識人や有閑階級にとっては、イデオロギーは対立していても、前衛映画そのものは両者に区別なく受け入れられました。そういう意味で、戦前の小型映画はごく自然に実験映画を内包していました。(荻野茂二作品を見た人ならうなずくことでしょう)。
もちろん、戦前の小型映画の中には、風景映画、ホームムービーの類も数多くありました。しかし、だからといって、それを「山川地蔵映画」(僕はこの言葉が嫌いですが、仕方なく使います)、と蔑視するのは浅薄というものです。当時はフィルムの性能、機材ともに素朴でしたので、20年代後半は現像して映っていたらラッキーだった時代なのです。そのような時代に名人クラスは、出来を「軟調」「硬調」と使い分け、編集のリズムもきちんと計算して作品を作っています。コンテスト上位入選クラスなら相当の腕前だったことが察せられます。少なくとも私が見た戦前戦後の小型映画作家の名手の作品の中に、「山川地蔵映画」はありません。例えば、映画にはリズムがなくてはならない、というムーシナック流の批評基準は当時の常識だったのです。
但しです。映画の主流が「前衛」であった時に、それを真似るのが果たして前衛的精神であるかどうかは別の問題です。同様に、「革命を嫌う愛国者」の作る作品が実験的かどうかも別の問題です。ただ、形式的には、戦前の小型映画は実験的映像を大いに楽しみ受け入れていました。
さて、前回書いた、「芸術は、創作者、作品、批評の3元構造の中に存在し、自己規定的で、感情の未知の領域を活性化するものである」という定義ですが、戦前の小型映画は、この定義を基本的には満たしています。作家本人の自覚という点からも、僕が「Fs」誌に連載している手島増次など、芸術至上主義者の典型のような人物でした。
ただし、上記の定義の中で「感情の未知領域を活性化する」、「自己規定的である」という点に関しては、戦前の小型映画は(プロキノ作品を含めて)、少し弱かったかもしれません。プロキノは内容主義、テーマ主義に凝り固まっており、さらに撮影技術が稚拙でしたので、その歴史的価値はともかく、作品そのものは幼稚だったと思います(実作を今日見れないので、僕は文献を拾った推理でこういうのです。間違っていたらお詫びしますが、まず間違いないでしょう)。
一方、より良き臣民である、上品な階級の作る小型映画は、技術批評と、道徳批評が中心でしたので、例えばダダイズムやシュールリアリズムに属すと思えるような作品に対しては、うまく批評機能が働きませんでした。矢野目源一(だったと記憶しますが)は、例外的に超現実主義映画の面白さを真っ先に批評した人ですけれど、小型映画コンテストでは、あまりスットンダ作品は、批評の対象から外される傾向がありました。いわゆる「オーソドクシー」が彼らの美学であり、技術至上主義で、予定調和的でした。
さらに付け加えることがあります。彼らは芸術性の高い作品を作ろうとする一方で、意識的に小型映画という「趣味」を持っていることの価値を力説しています。この時代、「高級な趣味のある生活」は、文化的生活をしている証でした。芸術である前に彼らは小型映画という趣味を誇っていたのです。当時農民がほぼ50%を閉めていた時代、民衆娯楽は大きな問題になっていました。権田保之助という有名な民衆娯楽研究の大御所も、趣味娯楽のある生活がいかに大切であるか力説しています。都市が形成され、週に一度の休日というライフサイクルが生まれ、都市住民が新しい趣味を持ちはじめた時に、もっとも高級な趣味とされたのが恐らく小型映画でしょう。
それには、当時の小型映画が基本的に「自家現像」であったこと、そしてこれはどんなに強調して模しすぎることはないのですが、特にパテベビーの機材の素朴さゆえに、機械を「自家工作」して改良することも小型映画趣味の楽しみだったことが、ここには関わっています。この点は戦後の小型映画と大きく異なる点です。小型映画の楽しみは、自家現像、改良にも大きく依存していたのです。
この背景には当時、ラジオ製作などの自家工作趣味が国民全般に大きく受け入れられていたことも影響しています。(これはドイツの国力発展を見て、国家が国民に奨励した面が強く、「子どもの科学」の発刊や、理化学研究所の設立など、一つの国策の線上にありました)。
プロキノは1934年頃には壊滅状態になります。愛国者側の小型映画活動は40年代の初期まで続きます。そして太平洋戦争の空白期を迎え、敗戦になります。
戦後の小型映画活動は個人的努力ではやくも終戦の年から始まります。それが活気を呈していたのは玄光社の「小型映画」誌の発行が続いた50年代半ばから80年代半ばの約30年間です。
さて、実験映画の発生ですが、55年の「キネカリグラフ」のような先駆的な作品を除けば、60年代半ばにスーパー8、シングル8が発売されて、小型映画趣味が大衆化したことが第一。第二には同じ時代に、ヨーロッパの前衛映画がアンリ・ラングロアの尽力で日本に一挙に紹介されるとともに、アメリカのアンダーグラウンド映画も同時に招来され、若い世代が戦前の前衛映画と同時代のアングラ映画に決定的に影響を受けたこと、の2大要因が決定的な役割を果たしています。
ヨーロッパ型前衛主義の流れからいえば、超現実主義とドキュメンタリーの弁証法的な止揚が大きな問題でした。一方、美術全般にはアンフォルメルとアクションペインティングが主流となり、アメリカのアンダーグラウンド映画は(これが日本の実験映画に最も影響を与えたのですが)、戦前のアメリカのアマチュア映画の規範を全て逆手にとるような、タブララサの段階にありました。適性露出への不信、安定した構図への不信、暴力的なパンニング・・・・・日本の若いアマチュア作家はアメリカのアングラ映画に決定的に影響を受けたこと、の2大要因が決定的な役割を果しています。
松本俊夫さんたちが「季刊FILM」を1968年から約5年間発行します。松本さんはそれ以前にも非常に刺激的な評論集を何冊か出していて超人的な活躍をされ、実験映画の理論的支柱となります。飯村隆彦さんも海外の、特に反芸術系の作家の動向について非常に啓蒙的な評論活動を行っています。一方、上映活動やアーカイブ化の体制作りはかわなかのぶひろ、富山夫妻の尽力によるものが大でした。今は亡き佐藤重臣さんもアングラブームの火付け役に大きく貢献しました。
60年代末までは、従来の小型映画作家と、新しい階層であるアングラ映画作家の活動は渾然としていました。
70年代になると、両者はかなり明確に活動の場を棲み分けるようになります。
そして小型映画作家の活動は80年代になると衰弱し、多くがビデオカメラへと機材を持ち替えていくのですが、実験映画のほうは逆に80年から「月刊イメージフォーラム」誌を刊行するなど、ますます勢力を拡大していきます。そして、80年代の半ばごろから日本各地の造形大学、美術大学などの系統に、何人もの実験映画作家が教師として勤めはじめます。
現代は、若者がフィルムやビデオを媒体とした芸術表現活動を志した場合には、否応なく、実験映画、実験映像の作家の教える教育機関に入らざるを得ない現状になっています。
さて本論です。小型映画は衰退したのに、なぜ実験映画は生き残り、文部省認定の大学教育カリキュラムにも編成されて、社会的に認知される芸術となり得たか、という本題について考えてみましょう。
僕は次の5つの点で両者を比較できると思います。
1、意図。
小型映画は「アマチュアリズム」と「趣味の昂揚」を自ら宣言していました。一方、実験映画サイドは、芸術派も反芸術派も「作家性」を重視しました。今西進化論のようですが、趣味を重視した小型映画は、自分の主張どおり趣味となり、芸術家を目指した実験映画は、思い通りに芸術になったわけです。
2、批評。
小型映画は基本的に技術至上主義の批評でした。ですから、その面で突出し、実験映画作家と小型映画作家の作品を見比べると、例えばカラーフィルムの発色性の点などでは、あきらかに小型作家の力量のほうが上です。一方、実験映画は作り手の主体性の問題や、美学の革新に力点を置き、作品における知覚の変革を通して、日常の知覚まで改革する、一種の革命論を背景に持っていました。
こういう力点の差が、実験映画には優れた批評家を作ることになりました。創作者・作品・鑑賞者という、芸術の3元構造から比較すると、実験映画は批評性に優れており、小型映画は、本格的な批評家を一人も生み出しませんでした。批評は学問の源泉です。最も優れた実験映画批評家である松本俊夫さんが、現在「日本映像学会」の会長に就任しているように、実験映画は批評の充実ゆえに、学際的になり、芸術化したのです。
3、階級。
階級の特徴は、批評の質を決定します。小型映画作家の階級は、戦前は愛国的で良識的なアッパークラスでした。戦後もその傾向は引き続き、非常に上品な階級が中心となります。8ミリ機材が大衆化した60年代後半からは必ずしもそうではなく、私のよく存じ上げている小型作家上田雅一氏などは労働組合の花形だったりしていますが、どちらかといえば、リベラルで上品な文化人という印象です。こういう上品な階級は相手をあからさまには批判しません。したがって批評も大変おだやかです。
それに比べて実験映画作家のほうは、いわば下品な階級でした。下品、というと語弊がありますが、僕はこの言葉に好感とユーモアを交えて使っています。具体的には、共産党員、新左翼、もしくはロマンティックな無政府主義者、これらの思想を持った人々が実験映画作家の中心を占めています。こういう人々は、上品な階級と比べると大変に議論好きで、徹底的に敵を攻撃します。
実験映画の批評の充実は、以上のような階級の特質と大いに関係があります。
4、教育機関への参入。
小型映画の教育は「芸道における師弟関係」でした。例えば東京の荻野茂二、大阪の沖中陽明の両氏が典型的ですが、彼らは個人的に「8ミリ教室」を開き、その場で弟子を養育していきました。一方実験映画は、イメージフォーラム付属映像研究所のような教育機関を作り、また造形大学、芸術工科大学、美術大学などに教員として進出していきました。その結果、前者は趣味的存在に留まり、後者は文部省お墨付きの芸術となったわけです。
5、美学。
小型映画は、これは戦後の場合ですが、日本の伝統的な文化を好んで取り上げました。例えば、郷土の特産品の製作過程を記録する文化映画的なもの、四季を素材にしたもの、日本情緒を重視したものなど、彼らは戦前の愛国的な市民の面影を継承して、日本の伝統文化を大切に作品の素材としました。一方、実験映画は、それ自体が欧米の前衛映画から直接影響を受けて成立したので、非伝統的であり、その意味では西洋志向でした。ナショナリズム対グローバリズムの違いと言ってもかまいません。
ところで、僕が芸術の条件としてあげた中の一つに「未知の感情、多種多様な感情を喚起する」という項目がありましたね。この点において、ナショナリズムの側は、その感動の質が伝統的で予定調和的になり、グローバリズムで、前衛志向、アングラ志向の陣営の作品は、その未知の感情を喚起する条件を大いに満たします。
さらに、もう一つ芸術の条件としてあげた「規範の自己規定性」の面でも前者はどちらかといえば規範重視的です。ただし、小型映画のアニメーションについては、アニメそのもののもつ特質(イメージの自由な飛躍)の点において、実験映画と区別しがたく、大変な名作が埋もれているはずです。
以上、要約すれば、「批評の充実」と「未知の感情の喚起」の点で、また「規範の自己規定性(形式の自由)」の点で両者には差異があり、このために小型映画は趣味視され、実験映画は必然的に芸術の条件を満たしていったのです。
しかし、小型映画は、趣味的気質を多分に持ちながらも、非常に優れた芸術作品を残しており、その発見と公開は今後の私たちの大きな課題として残っています。
実験映画はなぜ芸術として現在社会的に認知され、小型映画はなぜ趣味視されて忘れられていったのか。この問題に対して僕なりの考察を展開してきました。
けれど、何事にも再考、再々考が必要です。芸術となった実験映画は果たして趣味として留まった小型映画より高度なのでしょうか。実験映画にも反省すべき点があり、小型映画にも見習うことがあると、僕は思います。この次週はこのことについて、考えてみましょう。
 |
筆者20歳の写真
身長177cm、体重65kg。
詩と酒とバラの日々でした。
女からも男からもよくナンパされていました。 |
NO.5 ~小型映画から学ぶべきもの~
さて、前回は実験映画と小型映画の芸術性を比較した訳ですが、我が世の春を謳歌している実験映画にも、滅んでしまった文化/小型映画から学ぶべき点があると思うのです。
まず、技術力です。
私は世界的な8ミリ小型映画作家上田雅一氏の作品を、実験映画の世界ではトップクラスのテクニシャンと見なされている、ある作家に見せたことがあります。テレシネ版でしたが、その作家はどうしてもこの映像は16ミリだというのです。そこで後日上田氏に、あれは16ミリか、またはダブルランスーパーではないのか、と確認したところ、上田さん、にっこりして、いいえ、8ミリです、と答えられました。
理屈の上ではスーパーやシングルより性能の劣るレギュラー8を使っていながら、名人級の小型映画作家は、まるで油絵を見るような、時に日本画を見るような、見事な色彩に仕立て上げます。誰か技術に強い人に、この魔術のなぞ解きをしてほしいものです。
もう一つのエピソード。これも撮影技術の確かさでは定評のある実験映画作家の、とある受賞作品を、上田氏にぜひ見て欲しいと上映会に誘ったところ、上映途中で席を立たれたのです。理由を伺ったところ、あれはいけません、8ミリフィルムの能力を生かしていない、とのこと。
このような逸話が示すように、そこにあるものを写すという基本的な技術のレベルが、実験映画作家は小型映画作家の一流の人々の腕前から相当に遅れています。
確かに、実験映画は美学としては面白く、小型映画と比べるとはるかにアイロニーや脱構築性があります。しかし、逆に言えば、アイデアだけで勝負できる甘い世界だとも言えます。
ついで、小型作家の「謙虚さ」も見習うべき点でしょう。
小型映画作家が階級的に上品さという特徴を持っていることは前回書きました。その上品さの一環として、彼らはあえて自分を「芸術家」視せず、趣味人、または芸道の求道者と自覚している面が強く、このために、言動が大変謙虚です。
戦前の小型映画雑誌を開いてコンテスト入賞者の言葉を拾ってみると、大抵、拙作が入賞など、御恥ずかしい限りです。この作品はここが失敗しています・・・・・といった調子で非常にへりくだったコメントと出会います。
一方、実験映画作家の場合は、80年代以降にデビューした若手がとくにそうですが、調子に乗りやすいというか、たちまち自らを芸術家と自称しはじめます。
小型映画作家が国際コンテストで何度も入賞しても、キネ旬の監督辞典に名前が出ないのに対して、数本しか作品を撮っていない実験映画作家の名前が辞典に載り、あれっ、という間に学校の講師になったりしています。恵まれすぎの環境と言えるでしょう。
一流の小型映画作家でも、自分の創作活動を趣味や芸道と感じ芸術の一歩手前のものと自覚しているために、この謙虚さが生まれ、一方、どんな未熟な人間でも実験映画作家は自分が芸術を創作していると思い込んでいるために、ちょっと誉められるとすぐその気になって芸術家ぶり尊大になる。こういう、なんともいえない皮肉な現象が目に付いて仕方ありません。
この事と関連して、現代では受賞を狙って作品を作ることが当然となり、自己アピールのうまい作家が増えていますが、戦前は、受けを狙った作品を「当て込み映画」と言って蔑まれたものでした。
そろそろ本論に入りましょう。結論から先に言います。
「今後実験映像は必ずサロン化して堕落する」と僕は見ています。だから今後は「そのサロン化をどうやって防いでいくか」が実験映像の最大の課題である、と考えます。
すでにアメリカの実験映画はサロン化して衝撃力を失ったと言われます。アメリカだけでなく、僕が見たドイツ、カナダの実験映画のアンソロジーも多くは衝撃力を失った「おけいこごと」でした。今度は日本の番です。
戦後の実験映画は「アンダーグラウンド」映画として、既成の芸術に対抗して生まれました。いわゆるカウンターカルチャーです。非常に皮肉なことにそのアンダーグラウンドの表現が大学教育の中に編入され、文部省の認める正規の授業となりました。カウンターカルチャーではなく、映像を学びたい人間にとっての常識科目となったのです。
ここで、誤解をしてほしくないのですが、松本俊夫さんやかわなかのぶひろさん達が、大学の先生になったことを批判しているのでは決してありません。これらの人々は実績を積み重ねている内に自然とそういう社会的ステイタスを得たわけですし、後進の指導に邁進することはなんら悪いことではありません。実験映画のパイオニアであり貢献者であることは、言うまでもないことです。
問題は、「今現在の若者にとって実験映画は、アングラでもカウンターカルチャーでもなく、正規の芸術科目になってしまっている」というこの事実が、必ず作家の堕落とサロン化を引き起こすという点にあります。これは意地悪な意見でもなんでもありません。物理法則のように明確な原理から予測しているだけのことです。
アンダーグラウンドは地上文化、メジャー文化への抵抗でした。斜陽化しかけていたとしてもメジャーな映画製作会社があり、多数の人々が小型映画、アマチュア映画に手を染めていました。また、映画より先に文部省認定芸術であった音楽や、美術などがありました。アンダーグラウンドは体制の表現全般に反抗する若者たちのモードであり、同時に生き方でした。
松本俊夫さんが理研映画を辞め、金井勝さんが大映を辞め、鈴木志郎康さんがNHKを辞め、奥山順市さんがCMディレクターを辞めて、自主制作、個人映画の道を選びました。
現在は逆です。日本では映画産業は風前の灯火となっています。小型映画もとっくにブームは終わりました。
対抗すべきメジャーな映画がなく、実験映画そのものが大学教育の正規科目という形でメジャーな舞台に競りあがりました。若者はなにかに反抗するのではなく、ドロップアウトするのでもなく、むしろ、プロの商業映画監督やCMディレクターとなるために、教育機関で実験映画から学びはじめる状況になっています。
対抗文化としての実験映画の時代的役割はもう終わったのです。実験映像は今後、既成芸術である音楽や美術のように社会的認知を獲得していくと同時に、音楽や美術の教育のサロン化をあとから追いかけなぞっていくでしょう。
現代の美術教育や音楽教育が「ブルジョアジーの子弟のお稽古ごと」になっていることは、周知の事実です。
例えば僕たちは過去10年、20年の間に、音大や芸大の出身者の中から、何人の真の意味での芸術家を発見したでしょう。悪しき師弟関係、商業主義との癒着(特に美術は、美術年鑑を見れば分かるように見事にランク付けされて、商品化しています)・・・・・実験映像がこのような既成芸術の二の舞にならないためにどうすればいいのでしょう。
僕は8年前に次のように書きました。
「受容層が観客=実作者という円環の外に広がってゆかない芸術として実験映画は特殊であり、これは詩歌の同人誌活動に近い。このような自閉的な受容形態をしかし筆者は必ずしも否定しない。むしろ俳壇並みに発展し各地方に様々な流派が現れて競い合うとすれば現在よりまだ望ましいと思う。」(1992年5月発行「Fs」誌.p.40)
こう書いた時、僕の頭の中には現在の大学教育の姿が予想されていました。例えば造形大学のある教員の一門、多摩美のある教員の一門、あるいはイメージフォーラム付属映像研究所のある講師の一門、といったように、流派が生まれ、流派ごとに競い合う形になるにちがいないと。
そして同時に、その形態がサロン化して行くことも避けられない、とその当時から思っていました。僕はかなり皮肉な思いでこの部分を書いたことを思い出します。
では「実験映画がサロン化せず、ブジュジョアジーの子弟のお稽古ごとにならず、当初のアングラ性を失わないために」どうすればいいのでしょう。僕は次の3点が鍵を握っていると思います。
1、教師の指導力。
凡庸な教師は自分に似た作風の生徒を誉めることで、間接的に自作を誉めようとし、悪しき師弟関係を作ってしまいます。
有能な教師は、あらゆる異才を認める幅広い受容力を持っています。そして、悪しき師弟関係に陥らず、いわゆる「脱構築」の精神を生徒に十分に理解させ、大学教育の中にいながら大学教育を打ち破っていくような力の必要性を生徒に徹底的に理解させます。
この意味では、教師は非常に自覚的であるか、もしくは無自覚でいいかげんなほうがいいのです。一時期、大阪芸術大学の出身者や中退者が活躍した時期がありましたが、これは、この大学の指導が優秀だったからではありません。逆に、受験すれば誰でも合格するいいかげんな大学だった(今はどうだか知りませんが)ために、一般的な教養や技術の点では欠如していても、いわば異能の変人が集まり、異才を発揮することが出来たのです。
帯谷有理君など典型的な存在で、彼の批評はテキヤの口上のようにいかがわしくハッタリに満ちていますが、自己アピールの点では図抜けており、そのハッタリの計算が出来るので観客を飽きさせない新しい実験映画を作っています。
いずれにせよ、今後は各教育機関が競争しあって有能な作家を育てることが出来るかどうかにかかっています。その有能さというのは作品の善し悪しだけでなく、常に脱皮していく自己変革の能力を教えられるかどうかにかかっていると思います。
2、民間上映団体の活性化。
教育機関を出た後、プロにならなくても生き方として実験映像を作り続ける人間が多いほど、すそ野が広がり創作の質は切磋琢磨されます。福岡のFMF、解散しましたが関西のヴォワイアン、浜松のシネマ・ヴァリエテ、東京の、佐々木健、水由・片山夫妻の活動、山崎幹夫・山田勇男のラ・カメラ、老舗のハイロ、などなど、民間の上映団体には、人間的に魅力のある、牙を抜かれていない実験映像作家たちが頑張っています。
アカデミズムの悪い空気に染まった学生たちに民間派たちが実験的精神を実感させる形になればいいと思います。かつてヴォワイアンの代表だった平田氏は、このことを「街場の作家性」という言葉で表現しました。
これまでは民間の上映団体が中心になり実験映像作家を育てていたところに、80年代後半から大学教育の中で実験映像が教えられるようになり、民間の上映団体の意義が薄れていきました。
しかし、本当は今からこそ、これらの民間団体が、実験映像のサロン化や悪しきアカデミズムに対抗し、その欠陥部分を補完する役割をになっていると僕は考えます。VIEW JAPANの活動はその意味で今後の実験映画の鍵を握っていると思います。
3、作品の複製、販売の促進。
僕の原稿の第3信、第4信を通して、趣味と芸術を分けるうえで鑑賞者の存在、つまり批評がいかに重要かを述べてきました。実験映像は今のところ極く一部しかビデオ化、ディスク化されていません。しかし、これからは、どんどんビデオ化、ディスク化して、またDVDやCD-R、インターネットなどあらゆる媒体を通して、なるべく多くの人に、なるべく簡単に鑑賞できるシステムを模索しなければなりません。
そうすれば、どのような片田舎にいても実験映画を見ることが出来ます。すると、思わぬ地方から作家志望者、批評家などが飛び出してくる可能性があります。
また、さっき「Fs」誌の引用文に書いたように、これまでの実験映像は、実作者=鑑賞者、という自閉構造から抜けることが出来ませんでした。しかし、複製化と販売を進めることにより、実作はしないがその愛好者である人々が生まれてくる可能性が大いにあります。
このことは非常に大事なことで、中立的な鑑賞者、批評者の意見が実験映像に反映されることは、実験映像の現在にとって大変意味のあるカンフル剤になるのです。
例えば、実験映像が社会的に認知をされ、文部省教育の中に編入されたことで、否応なくサロン化、堕落の道を通る、という僕の意見は、外から見ていれば明々白々のことなのですが、中で教育している当人には、非常に見えづらく、見えたとしてもいいづらいことでしょう。フリーな立場で単なる愛好者だからこそ好きなことがいえる訳です。
とにかく、実験映像の自閉的円環を脱却するには、作品をどんどん複製化し販売することです。これは、作家に収入を与えるという面でもメリットがあります。
以上、ここでは小型映画から学ぶべき点について、そして実験映像の教育環境が整備されたことによる危険さについて述べました。
最後に一つ、実験映像は、1930年前後と1970年前後、そして1980年代半ばに一種のピークを迎えました。この3つのピークのうち、30年前後と70年前後は、思想としてマルクス主義があり、同時に共産党の不徹底さに苛立つ新左翼の運動があり、芸術表現の過激さは、これらの社会動向と思想とパラレルの関係にありました。
しかし、コミュニズム神話の崩壊のあとは、共同幻想としての革命思想を多くの人が喪失してしまいました。松本俊夫さんの場合は、マルクス主義から記号論、ポストモダニズム、と常に理論武装が出来ているようですが、大半の作家にとって70年代後半以降は、状況を変革するための理論、行動規範が持てないでいるのです。
「社会変革の夢を喪失した時代の、芸術の革命」という、矛盾した、非常に気のぬけた状況を前に、作家たちは形式的に洗練に向かう、あるいは自らの精神的疾病を武器として消耗する、などしてこの総保守化の時代が過ぎ行くのを待っているようにさえ見えます。
これからは、共同幻想としての革命が見えなくても、また体系化されていなくても、教育者個々が革命思想、自己変革の理論と感性を模索し、磨き上げ、それを教え子達に感染させ、展開させていく時代でしょう。ちょうど金井勝さんの「時が乱吹く」を見た人々が、個人個人の心の中に、何ともいえない前衛精神の爆発を感じ取って、いつまでも脳細胞の一部分に、まだまだ、まだまだ、の声を響かせているように・・・・・・・。
 |
1500本の
ビデオコレクションの前で
筆者当年44歳。
身長177cm、体重90kg。
もはや詩も書かず、
我がバラの花たちは去り、
あるいは枯れしぼみ、
ひたすら酒太りの毎日です。 |
5回に及んだ連載はこれで一応終了します。
また、新しい構想が生まれたら寄稿します。
では、いつかまた。
◎ 寄稿 「子猫に寄せる」
※ HP 那田尚史の部屋へようこそ